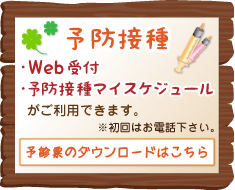~中山通信~ 急性胃腸炎
昨年の12月から胃腸炎の流行が続いています。この4ヶ月の間に増加減少を繰り返し、クリニックでは患者さんが途切れることがありません。急性胃腸炎・感染性胃腸炎・ウイルス性胃腸炎など呼び名はいろいろありますが、表現の仕方により名称が変わるだけで同じものと考えて差し支えありません。
通常、胃腸炎の原因のほとんどはウイルスで«ノロウイルス»«ロタウイルス»が有名ですが、それ以外にもたくさんあり、この4ヶ月で数回かかった方もいます。現在の流行の中心は«アストロウイルス»«サポウイルス»です。食中毒などの集団発生ではノロウイルスが多いですが、通常の感染ではそれほど多くはありません。アストロウイルスもサポウイルスもノロウイルス同様に感染力も強く、嘔吐・下痢を起こしますので、ノロウイルスなどと同様に注意が必要です。ノロウイルスでなければ良いというわけではないのです。
ウイルスを原因とする感染性胃腸炎には特別な治療方法はなく、つらい症状を軽減するための処置(対症療法)が行われます。乳幼児や高齢者では下痢等による脱水症状を生じることがあるので、早めに医療機関を受診することが大切です。特に高齢者は、誤えん(嘔吐物が気管に入る)による肺炎を起こすことがあるため、体調の変化に注意しましょう。嘔吐の症状がおさまったら、少しずつ水分を補給し安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるように心がけましょう。
★感染予防のポイント★
① 感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスはアルコール消毒の効果が乏しいため、まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。特に排便後・調理や食事の前には、その都度石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
② カキなどの二枚貝を調理するときは中心部まで十分に加熱しましょう。
(中心温度 85~90℃で 90 秒間以上の加熱 * が必要です。)*「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省)より
③ 吐物や糞便は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤)を使用し適切に処理しましょう。
④ 吐物や糞便を処理する際は、できれば使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
⑤ 糞便・吐物との接触ばかり取り沙汰されますが、実際の感染は飛沫感染が多いです。
通常の風邪やインフルエンザ・新型コロナウイルスと同様マスクの予防効果も高いので、特に家族が発症した際にはマスクをすることもおすすめします。
中山医院 院長 中山豊明