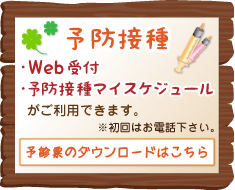~栄養士講座~ 「食事のマナー≪お箸のはなし≫」
近年、家族そろって食事をする共食が減って、ひとりで食べる孤食が増えています。
食習慣や価値観などが変化してきていますが、食事のマナーも食育のひとつです。こどもに間違った食事の仕方を伝えてしまうことにならないよう、家族みんなの食事マナーを見直してみましょう。箸を正しく持つことは、気持ちよく食事をすることに繋がり、食事を楽しむために改めて知っておいてほしいことです。
食べやすい箸の持ち方は、箸先から約3分の2の部分を持ちます。上の箸は鉛筆と同じ持ち方をし、下の箸は中指と薬指の間に入れて固定します。物をつまむ時には、中指と人差し指と親指で上の箸を動かして、下の箸は動かしません。
こうすると、自在に物がつかめます。
また、人前で恥ずかしいとされる「きらい箸」には気を付けましょう。
・料理を箸で串刺しにして食べる刺し箸
・どれを食べようか迷って箸を料理の上で動かす迷い箸
・器を箸で引き寄せる寄せ箸
・箸と箸で料理を受け渡しする渡し箸
・箸先で人や物を指す指差し箸
・箸をご飯の上に立てる突き立て箸
などは良く耳にするのではないでしょうか。
日頃から当たり前のように使っている箸は一度身についてしまった持ち方を修正したくても、なかなか難しいといわれます。しかし、自分で気を付ければ大人になってからでも正しい持ち方を身に付けることはできますので、正しい持ち方で箸を使う快適さを知ってほしいですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~中山通信~ 急性胃腸炎
昨年の12月から胃腸炎の流行が続いています。この4ヶ月の間に増加減少を繰り返し、クリニックでは患者さんが途切れることがありません。急性胃腸炎・感染性胃腸炎・ウイルス性胃腸炎など呼び名はいろいろありますが、表現の仕方により名称が変わるだけで同じものと考えて差し支えありません。
通常、胃腸炎の原因のほとんどはウイルスで«ノロウイルス»«ロタウイルス»が有名ですが、それ以外にもたくさんあり、この4ヶ月で数回かかった方もいます。現在の流行の中心は«アストロウイルス»«サポウイルス»です。食中毒などの集団発生ではノロウイルスが多いですが、通常の感染ではそれほど多くはありません。アストロウイルスもサポウイルスもノロウイルス同様に感染力も強く、嘔吐・下痢を起こしますので、ノロウイルスなどと同様に注意が必要です。ノロウイルスでなければ良いというわけではないのです。
ウイルスを原因とする感染性胃腸炎には特別な治療方法はなく、つらい症状を軽減するための処置(対症療法)が行われます。乳幼児や高齢者では下痢等による脱水症状を生じることがあるので、早めに医療機関を受診することが大切です。特に高齢者は、誤えん(嘔吐物が気管に入る)による肺炎を起こすことがあるため、体調の変化に注意しましょう。嘔吐の症状がおさまったら、少しずつ水分を補給し安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるように心がけましょう。
★感染予防のポイント★
① 感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスはアルコール消毒の効果が乏しいため、まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。特に排便後・調理や食事の前には、その都度石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
② カキなどの二枚貝を調理するときは中心部まで十分に加熱しましょう。
(中心温度 85~90℃で 90 秒間以上の加熱 * が必要です。)*「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省)より
③ 吐物や糞便は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤)を使用し適切に処理しましょう。
④ 吐物や糞便を処理する際は、できれば使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着用し、処理後は石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
⑤ 糞便・吐物との接触ばかり取り沙汰されますが、実際の感染は飛沫感染が多いです。
通常の風邪やインフルエンザ・新型コロナウイルスと同様マスクの予防効果も高いので、特に家族が発症した際にはマスクをすることもおすすめします。
中山医院 院長 中山豊明
~栄養士講座~ 「ちょうどよいバランスの食生活を考えてみましょう」
4月は新しい環境になるという人が多くなります。仕事や学校、習い事などやりたいこともやらなくてはいけないこともたくさんありますよね。
健康な体と心を保つために、食生活の見直しをお勧めします。食事バランスについては、次のことに注意してみてください。
①三大栄養素のバランスが大事!
1日に必要なエネルギー量(カロリー)であれば、どんな食べ方でもOKと思っていませんか。
ヒトが生きていく上で必要な栄養素はたんぱく質、脂質、炭水化物ですので、偏らないことが大切です。
炭水化物の摂りすぎになりやすいのは主食の重ね食べです。おにぎりとカップめんなど、おかずが少なくなるとたんぱく質が不足しがちになります。
脂質の摂りすぎになりやすいのはカルボナーラとケーキなど、油脂(バター)や生クリームの重ね食べに注意が必要です。ざっくりと「主食」「主菜」「副菜」がそろっているか確認すると良いですね。
②1日2食だと必要な栄養素を摂るのは難しい!欠食しないこと!
特にカルシウムと食物繊維はもともと摂取量が少なめですので、より少なくなってしまいます。
③栄養バランスだけでなく生活リズムや家計などのバランスも考えて
特に野菜不足は気になるけれど高価でためらってしまう場合には、冷凍野菜を上手に使うと良いです。収穫後すぐに急速冷凍されたものなので栄養素に違いはほとんどありません。
ご家庭でのちょうど良いバランスについて考えてみてください。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「お米の栄養」
私たち日本人の食生活は選択肢が増えて多様化しています。
近年では健康のためにお米を食べないという人もいるようですが、本当に良いのでしょうか。
お米の栄養成分の7割以上は炭水化物で、生きていくためのエネルギー源となります。炭水化物と糖質は同じものと思われがちですが、実は炭水化物とは「糖質」と「食物繊維」を合わせたものを指します。そしてお米には脂質が少ない特徴があり、たんぱく質も含まれています。エネルギー源となる炭水化物と体をつくるたんぱく質の両方が摂れる、理にかなった食品と言えますね。
お米の1人あたりの消費量は少なくなっています。お米は太ると思って食べないようにしているという方もいるでしょう。しかし人が太ったり痩せたりするのはエネルギーの摂取と消費のバランスが取れていないことで起こるものであり、糖質だから太るということではありません。
どのような食事でも、摂取エネルギーが消費量よりも多ければ脂肪として体に蓄積されやすくなります。バランスが大切なのであり、お米を食べると太るという訳ではないのです。
お米は腹持ちが良く、脂質が少ないこと、糖質だけでなく食物繊維も含まれる点から体脂肪になりにくいとされています。必要な量は年齢や性別、活動量によって異なりますが、毎食茶碗1膳分くらいは食べるようにしたいですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~ 中山通信 ~ ヒトメタニューモウイルス(hMPV)
年末年始のインフルエンザの猛威が1月後半から急に落ち着きましたが、発熱でクリニックを受診されるお子さんはまだ多い印象です。インフルエンザの陽性者が減っているという事は、それ以外の感染症での発熱という事になります。
そのうちの一つ、昨年末からアジア各地で流行と報じられている【ヒトメタニューモウイルス】についてお話ししたいと思います。
このウイルスは気管支炎などの呼吸器感染症をひきおこすウイルスの一種で、大人にも感染することはありますが、1~3歳の幼児の間で流行することが多いです。小児の呼吸器感染症の5~10%、高齢者の呼吸器感染症の2~4%は、
このウイルスが原因だと考えられています。2歳までに約30%、5歳までに約75%、10歳までには、ほぼ100%が一度は感染するといわれます。潜伏期間は4〜5日です。
鼻水や咳(せき)とともに38.5℃以上の高熱が出る場合が多いです。嘔吐や下痢も7〜8%近くのひとにみられ、最初は急性胃腸炎と診断されることもあります。 また発熱が平均して4~5日続くため、 インフルエンザと間違われることも少なくありません。
喘鳴(ぜーぜー)する症状も60%近くの方にみられます。このように経過は通常の風邪よりは長い傾向にありますが、1週間程度で徐々に症状は治まってきます。しかし、1回の感染では充分な免疫が獲得できないことがわかっており、
何度か繰り返して感染→年齢が上がるにつれて徐々に免疫がつく→症状が軽くなる という経過をたどります。インフルエンザや新型コロナのように抗原キットで診断できますが、特に特効薬もなく、治療は年齢と症状に応じた対症療法となります。またインフルエンザや新型コロナウイルス感染症のように学校安全保健法の出席停止に当てはまる疾患ではないため、早期に診断する必要はないと考えられます。
参考文献
Ebihara T et al. J Clin Microbiol 2004
中山医院 院長 中山豊明