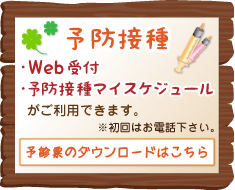~院長講座~「インフルエンザ罹患後の接種」
Q 先日インフルエンザにかかってしまいましたが、
この冬のインフルエンザワクチンは受けた方が良いでしょうか
インフルエンザは、「1シーズンに1度感染すれば、そのシーズンはもう感染しない」というものではありません。今年は、冬にA型インフルエンザにかかった人で、最近、A型のインフルエンザに罹患した人も数人いらっしゃいました。
ヒトが感染するインフルエンザウィルスには大きく分け4種類あり、
さらにA型ウィルスは構造によってさらに多くの種類があります。それらのウィルスはさらに小さな変異を繰り返すので、まったく同じウィルスにしかかからない保証はありません。
同じインフルエンザでも、種類が違えば別のウィルスなので、免疫ができていても感染してしまうのです。
このことから、同じウイルスでも小さな変異を起こせば、この冬に感染する可能性があること、インフルエンザウイルスには4種類の流行型があり1度かかっても他の3つにかかる可能性があることが考えられますので、
「今年インフルエンザにかかってもワクチンを打つ意味がある」ということになります。
インフルエンザは一度かかると高熱や咳・鼻水・全身のだるさ・筋肉痛といった症状が5日から7日程度続く、たいへんしんどい病気です。
ワクチンで予防、軽症化させることをお勧めします。
中山医院 院長 中山豊明
~栄養士講座~「旬を楽しみましょう」
日本では昔から、旬の食材を楽しむ習慣があります。
旬とは、ある特定の食材においてほかの時期よりも新鮮でおいしく食べられる時期をいいます。また、旬のものは市場に出回る量も増えるので値段も安価になりやすく、うれしい時期といえます。
9~10月頃の旬の食材は、栗、ごぼう、さつま芋、里芋などがあります。
11月頃から冬の旬の野菜である、かぶ、小松菜、大根、長ネギ、白菜、ほうれん草などが出回ります。
実は、旬の食材は栄養成分も豊富といわれています。ほうれん草は店頭に1年中並んでいますが、旬の出回り期とそれ以外の時期で栄養成分にどのくらい差があるのか、調べたデータがあります。含まれるビタミンCの量を100gあたりで比較してみたところ、12月(旬の出回り期)では84㎎あるのに対し、9月には17㎎しか含まれていなかったのです。1年間の平均は43㎎とされていますが、時期によって栄養素にも差があるということですね。
野菜や果物は1年中手に入れることができますが、何の食材が旬なのか、お子さんと一緒に考えて季節に合った食材、献立を心がけることが食育にも繋がります。
お子さんが苦手な食材があるのなら、旬の時に一緒に料理をして食べるチャレンジがおすすめです。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「間食を上手に取り入れましょう」
間食というと、太るから控えるものというイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?
間食とは、食事と食事の間に食べるもののことを言います。また、こどもの間食には捕食の意味もあります。「おやつ(お菓子)=間食」ではない、と考えてみると良いですね。
もちろん、おやつやお菓子は心の栄養剤ととらえて、適量を食べるのは構いません。しかし、成長期のこどもは、発育・発達にエネルギーや栄養素が使われるので、1日3食の食事だけでは賄えず、間食(捕食)が必要になることがあります。
部活や塾などで夕食が遅くなりがちな場合は、その前に主食(おにぎり、サンドイッチ、パンなど)を捕食として食べることがおすすめです。主食は主にエネルギー源である炭水化物を補給でき、活動力やパフォーマンスを維持することができます。
また、食事の時に食べられなかった不足している栄養素を補給することも良いでしょう。例えば、食事の時に乳製品が少ないと思ったら、間食にヨーグルトや牛乳を摂ってみる、果物がすくなければバナナやりんごなどを摂ると良いですね。
ただし、間食の量は年齢や性別、活動量などによって個人差があります。気になるという方は、栄養相談をご利用ください。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「子どもの睡眠について」
子どもの生活時間の夜型化が進んでいるといわれています。生活が夜型になると、睡眠時間が減少する傾向にあります。ある調査によると、22時以降に就寝する子どもの割合は、1歳6か月、2歳、3歳で半数を超えているそうです。
睡眠不足は、成長の遅れや食欲不振、注意や集中力の低下、眠気、疲れやすいことなどをもたらします。子どもの場合は眠気を意識することができなくて、イライラしたり、多動や衝動行為があったりすることがあります。
また、睡眠不足が将来の肥満に繋がるといわれており、起きている時間が長くなれば、それだけ余分に間食・夜食などを食べてしまうことが原因のひとつです。
睡眠を妨げる肥満による睡眠時無呼吸症候群は子どもにも増えており、適切な睡眠習慣と生活リズムを作ることが大切になります。
早寝早起きをすると良いとは言いますが、難しい場合は朝の早起きから始めると良いです。これは、朝起きて太陽の光をあびて体内時計をリセットすることで、徐々に朝起きて眠くなるまでの時間を夜型から朝型に戻していくことが出来るからです。
朝早く起きられれば、朝食を食べて、体温を上げて元気に活動することも出来ますね。ぜひ長期休暇にもお子さんの睡眠を見直してください。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「熱中症対策のポイント」
日々気温が上昇し、暑くなってきました。
こどもは大人よりも熱中症になりやすいと言われています。それは、体温調節能力が未発達なことなどから、高温時や炎天下で体の深部体温があがりやすいからです。高温環境下にいると、熱中症のリスクが増してしまいます。こどもを熱中症から守るためのポイントは、
①顔色や汗のかき方を十分に観察すること
顔が赤く、ひどく汗をかている場合は深部体温がかなり上昇していると考えられるので、涼しい場所で十分な休息が必要です。
②のどの渇きに応じて適度な水分摂取ができる(自由飲水)能力を磨く
水分摂取量の目安はこどもの体重によって違います。汗のかき方によっても変わります。のどが渇いてから飲むよりも、こまめに水分摂取をすることがおすすめです。
③日頃から暑さに慣れるため適度に外遊びをすること
④服装を選ぶ
こどもは自分で環境にあった衣服の選択や着脱をする十分な知識が身についていません。そのため、保護者が熱のこもらない服装や、環境に応じた着脱を適切に指導しましょう。
また、晴天時は地面に近いほど気温が高くなります。大人が暑いと感じるときは、こどもはさらに暑いということを忘れないようにしましょう。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美