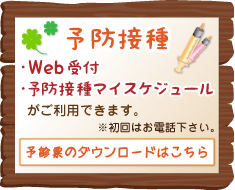栄養士講座「毎年6月は食育月間です」
じわじわ気温が上がり始めていますね。体調の変化に注意して過ごしていますか?
6月は食育月間です。平成17年に食育基本法が制定・施行されて16年目になります。
毎日の食について、何についてでも構いません。ご家族で見直したり話し合ったりしてみませんか。
例えば、好き嫌いを克服するために色々な食べ物にチャレンジすることも良いですね。野菜嫌いな人は、匂いが苦手なのか、食感が嫌いなのか、味そのものなのか理由は様々です。
野菜に含まれるビタミン類やミネラル類、食物繊維が不足しがちになるので、少しでも食べられるものから増やしていきましょう。苦手な野菜を素揚げにして、カレーライスに乗せて食べてみるのはいかがでしょうか。
チーズやマヨネーズとあわせてグラタンにするのもおすすめです。味が変わると食べられることもありますし、食わず嫌いのこともありますので、違う料理にして食べてみるなどしてみてください。
食材が本当においしい旬の時期に食べてみる、新鮮なものを使うだけでも違います。出来れば自分で野菜を育ててみるのも良いでしょう。ぜひ、食べることについて、考えてみてください。
メイプル 管理栄養士 佐野文美
院長講座「あせも」
あせもは、夏に多くみられる皮膚トラブルのひとつで、大量の汗をかくことで汗腺が詰まり、皮膚内に汗がたまって生じます。
こんな書き方をすると汗が悪者のように思われてしまいますが、汗の成分はその9割が水分で、残りも塩分やミネラルなど、体にとって必要なものばかりで、けっして汗そのものが不衛生というわけではありません。
むしろ皮膚を乾燥から守ったり、体温を調節したりするなど、私たちの体にとって重要な役割を担っています。とくに夏は汗をかくことで体温を下げる効果があるため、汗はきちんとかいた方が良いのです。
ただ、たくさん汗をかいた後、放置するとあせもなどの皮膚トラブルを引き起こすため、自分で汗をふけない小さな子どもは特に、あせもができやすくなります。
では、子どものあせもはどうやって治しましょうか。
●おむつはこまめに取り替える
●直接肌にあたる衣類は、吸水性・通気性が高いものを選ぶ
●定期的に、汗をかいていないかチェックする
●汗をかいたら、こまめに乾いたハンカチやタオルでやさしく拭き取る
●大量に汗をかいたら、ぬるめのシャワーや沐浴で汗を流す
●かゆみが強い場合は、冷たいタオルなどで冷やす
適切なスキンケアであせもはある程度治りますが、ひどい場合には、
ステロイド外用剤の使用が必要です。
こどものクリニック中山医院 院長
栄養士講座「バランスよくお弁当をつくろう」
新緑の季節になりました。
春以降、お弁当をつくるようになったという方は多いのではないでしょうか。お弁当箱に、栄養素のバランスを崩さずにきれいに詰める方法を知っていますか?「3・1・2お弁当箱法」といいます。まず1つめのルールは、自分に合った大きさのお弁当箱を選ぶこと。3~5歳のこどもなら容量が
400mlくらいのものを選びます。2つめのルールは、中身が動かないようにしっかり詰めること。隙間があると崩れやすくなり、容量よりも少なくなってしまいます。3つめのルールは、3:1:2=主食(ご飯):主菜(肉、魚、卵中心のおかず) :副菜(野菜中心のおかず)の面積比にすることです。どういうことかというと、お弁当箱の半分に、ご飯を詰めます。残った1/2の面積をさらに3つに分けて、そのうち1つ分にメインのおかず、2つ分に野菜などのおかずを詰めると良いです。こうすると、ほぼ容量分がおおよそのエネルギー量になるといわれています。
バランスの良いお弁当で、見た目もきれいにできると、作る側も食べる方もうれしいですよね。
ぜひ実践してみてください。
メイプル 管理栄養士 佐野文美
院長講座「花粉症に対するこどもの免疫舌下療法」
舌下免疫療法は、アレルギーとなる原因物質を含んだ内服薬を舌下に投与することで原因物質に対するアレルギーが現れないように体を少しずつ慣らしていく治療方法で、ステロイド薬やアレルギー剤のように症状を押さえ込む薬ではなく、体質を変えて根本から治していく画期的な治療法です。
痛みや副作用も少ないので小児にもおすすめです。抗アレルギー剤は飲むのをやめると効果が消えますが、舌下免疫療法をすると、やめた後も効果が続きます。
現在は、スギとダニに対しての舌下免疫療法が行えます。スギで約8割の方にダニで7割の方に有効といわれています。
治療期間ですが、まず、1〜2年間での効果を確認します。効果があれば合計3〜5年間の治療を行います。効いているか否かも、1〜2年みないとわかりません。また、短期間で治療を終了すると、治療終了後の効果が持続しないと考えられますし、お薬は毎日服用しなければなりません。
スギ花粉症、ダニアレルギーともに5歳以上から開始することができます。お子さんでも、舌下免疫療法は是非とも試みてほしい治療法です。
当院でも行っております。ご相談ください。
栄養士講座「和食の食文化を大切にしましょう」
だんだん暖かくなり、春めいてきました。
皆さんが普段よく口にする食事は、和食と洋食どちらが多いでしょうか。
和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され、世界でも食に関する無形文化遺産はあと6種ほどあります。和食の特徴は、日本の国土がもたらす多様で新鮮な食材があり、その味を尊重していること、一汁三菜を基本とする食事スタイルは栄養バランスがとりやすいといわれていること、自然の美しさや季節の移ろいを表現すること、年中行事と密接に関わっていることです。
昔から日本人は、自然を敬い、節目の行事や伴う食事の作法やしきたりをつくり、その恵みに感謝する心から食材を無駄なく大切に使う加工技術や調理法を生み出しています。出汁のうま味や発酵食品を上手に使うことによって、動物性油脂の少ない食生活ができ、長寿や生活習慣病の予防に役立っているといわれています。米が主食というだけで、パン食よりも塩分が少なく出来るということも良いとされていますね。
調理方法の工夫なども、栄養相談ではお話していますので、ご興味のある方はお声掛けくださいね。
メイプル 管理栄養士 佐野文美