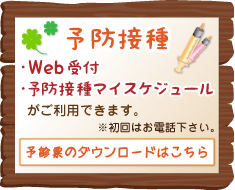栄養士講座「必要な水分量について」
今年は暑さがとても厳しいですが、上手に水分を摂っていますか?
水分は体を構成する大切な成分で、幼児で約70%、成人男性で約60%、成人女性と高齢者で約50%程度は水分が占めています。
体内の水分を20%失うと死亡する恐れがあるといわれ、水は人間にとってとても大切なものです。健康のために水を飲もうという取り組みが、厚生労働省後援のもと行われています。
熱中症だけでなく、脳梗塞、心筋梗塞など様々な健康障害を予防するためにも
こまめに水を飲みましょう。喉が渇いたと感じたら脱水の可能性もあります。
朝起きたとき、入浴後、寝る前、スポーツの前後に水分を摂るようにしてください。
1日の必要な水分摂取量は、成人の場合、食事から0.6~1ℓ程度・飲み水で1.2ℓ程度・体内で作られる水(代謝水)が約0.3ℓ程度とされています。子どもの水分の目安は年齢によって異なりますが、体重1㎏あたり、2歳児で115~125ml(体重12㎏の場合約1400ml)6歳児で90~100ml(体重19㎏の場合約1800ml)必要とされています。
水分補給は、早めにこまめにおこないましょう。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
院長講座「熱中症」
だんだんと暑くなってきて、熱中症が心配される季節になってきました。
子どもは体温の調節がまだうまくいかないので、熱中症になりやすいともいわれています。日常よくみられるのは 熱疲労 という状態で、
●軽度から中等度の脱水がありますが、体温はそれほど上昇していません
●めまいや頭痛に加え、筋肉の痙攣(こむら返り)が起こることもあります
●おなかの症状があるのも特徴で、おなかの臓器への血流が悪くなったり、
めまい自体が吐き気や嘔吐を引き起こすと考えられています。
この状態で放っておくと悪化して重症化してしまう可能性があるので、気づいた時点でなるべく早く対処する必要があります。熱中症になっても、初期のうちに適切な対処をすれば進行を防げます。もしかしたら熱中症かも!と思ったときに、まずやるべきことをみていきましょう。
「涼しい場所に移動する」
熱中症は屋内・屋外問わず、外気温や湿度が高いときに発症します。
屋外:風が通る日陰、屋内:できれば空調できる場所への移動が望ましいです。
衣類も脱がせるかなるべく緩めるようにし、風が通るようにして寝かせてあげましょう。
「体を冷やす」
体の中で大きな血管が通る部位を積極的に冷やしましょう。
具体的には、首の後ろ、脇の下、太ももの付け根です。
低温やけどしないように注意しながら、氷嚢やアイスノンを当ててあげましょう。すぐにこうしたものが手に入らない場合には、自販機などで売っている冷えたペットボトルでも代用できます。
また、熱を逃すために、表面を少し濡らしたあとにうちわなどで扇ぐのも効果的
です。薬局などで販売しているジェルシート(冷えピタ)は体温を下げる効果はないので、注意しましょう。
「水分を摂らせる」
意識がはっきりしているようであれば、冷たい水分を与えて中から冷やすのも効果的です。熱中症では脱水は必ず存在するので、脱水の補正と、体温を下げることの両方に有効です。水分はお茶や水ではなく、必ず経口補水液など塩分を含んだものにしましょう。
経口補水液が手に入らない場合には、自作することもできます。
水500mlに対して塩ひとつまみと砂糖大さじ2杯程度が適切な分量です。
こどものクリニック中山医院 院長
栄養士講座「夏の食べ物と作用」
暑い日が続いていますね。
早くも夏バテや暑気あたりなどの症状が出ている方もいるのではないでしょうか。
旬の食材を摂る事は気候や風土を考えた上でとても良いとされています。夏が旬の食べ物にはどんな作用があるでしょうか。
●『きゅうり』・・・ 熱を冷まし、余分な水分を排出する作用があります。暑気あたりに良いとされ、胃腸が弱っている場合は加熱して食べると良いです。
●『オクラ』・・・ 熱を冷まし、ネバネバ成分が胃の粘膜を保護して胃の働きを助けてくれます。
●『スイカ』・・・ 体内にこもった熱を冷ます清熱作用と、水分調節作用があります。ただし、体を冷やすので胃腸が弱っている時や冷え性、下痢体質の人は食べ過ぎに注意しましょう。
他にも、アスパラガス(初夏頃)、とうもろこし、トマト、なすなども旬の野菜です。汗とともに失われがちなミネラルを食材から摂れるようにしたいものです。また、卵や豚肉などに多いビタミン群を摂ると糖質がエネルギーに変わりやすくなり、スタミナ増強につながります。たんぱく質も忘れずに摂ってくださいね。
夏も元気に過ごすため、バランスの良い食事を目指しましょう。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
院長講座「食中毒にご注意ください」
食中毒の主な原因である細菌は、気候が暖かく、湿気が多くなる梅雨から夏にかけて増殖が活発になります。とりわけ、
- 食肉に付着しやすい
・「腸管出血性大腸菌(O-157、O-111など)」
・「カンピロバクター」
- 食肉のほか卵にも付着する
・「サルモネラ」
による食中毒の発生件数が目立ちます。
食中毒は家庭で発生することも珍しくありません。
特に肉や魚には、食中毒の原因となる菌やウイルスがいることを前提として考え、その取り扱いに気を付けましょう。
厚生労働省では、
「食中毒菌を『つけない』『増やさない』『やっつける』」
を食中毒予防の3原則として掲げています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物につけないよう、こまめに手を洗いましょう。包丁やまな板など、肉や魚などを扱った調理器具は使用するごとに洗剤で洗い、できるだけ殺菌するようにします。
また肉や魚の汁が他の食品に付着しないよう、保存や調理時に注意が必要です。細菌の多くは10℃以下で増殖のペースがゆっくりとなり、マイナス15℃以下で増殖が停止します。
☑肉や魚、野菜などの生鮮食品は購入後、すみやかに冷蔵庫に入れてください
☑庫内の温度上昇を防ぐため、冷蔵庫のドアを頻繁に開けることや食品の詰め込み過ぎはやめましょう
☑ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅するので、しっかり加熱して食べましょう
☑肉や魚、卵などを扱った調理器具は洗って熱湯をかけるか台所用殺菌剤を使って殺菌しましょう
こどものクリニック中山医院 院長
栄養士講座「便秘について知っておきたいこと」
梅雨時期になりました。体調管理は出来ていますか?
食べ物を食べると、栄養の大部分は小腸で吸収、その残りは大腸へ送られます。水分は小腸と大腸で吸収されるので、大腸を移動している間にどんどん吸収されて、便塊を作り、排便されます。
排便の回数は1日2~3回から2~3日に1回くらいまで、人によって幅があるため、排便習慣で全く苦痛が無ければ必ずしも便秘と考えなくても良い場合があるとされます。
便秘の原因は様々で、
便を押し出す力が十分でない
食事の摂取量が少ない
病気のため などがあります。
便秘予防には、規則正しい食習慣を持つことが大事です。食事量が少なくて、食物繊維の量が減ってしまうことで便秘になることも。食物繊維以外にも、水分や脂質を適量摂取しているかも気にしてみてください。腸内環境も大切です。プロバイオティクスとは、有益な効果を与える微生物(乳酸菌やビフィズス菌など)のこといい、腸内環境の改善に役立つといわれています。これらは摂ってすぐに効果がでるわけではなく、継続的に摂取することが良いとされています。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美