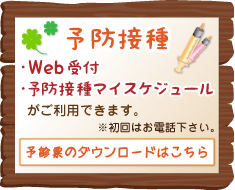院長講座「乾燥する季節のスキンケア」
乾燥期の冬は、肌の水分量不足と空気乾燥などにより、皮膚中の水分が出ていく一方なので、水分を保持しにくくなり、うるおい不足に陥ります。そして外的刺激から守る肌のバリア機能も低下しがちです。とくに子供の場合、皮膚は大人よりも薄く、皮脂の分泌も少ないので、大人の肌と比べて水分を体内にとどめる働きが未熟なので、どうしても乾燥肌になりやすいのです。ちょっとした刺激に敏感に反応し、炎症や痒みといった肌トラブルにつながることもあります。肌が乾燥した状態が続くと、外的刺激に弱くなり、ちょっとした刺激にも敏感に反応するようになります。
子供の肌を乾燥から守るには、肌乾燥を予防すると共に効果的な保湿が必要です。具体的には軟膏や保湿クリーム、ベビーローションなどの保湿剤を使うのがおすすめです。お肌のコンディションと合わせて、丁寧に保湿ケアを行うことで、皮膚中にたっぷりの水分が、備わります。うるおいを逃がさないためのフタをする効果もあります。一般的に、保湿を行うタイミングは、お風呂上がりが最適です。お風呂といえば、お風呂の温度も注意が必要です。冬場は気温が低いのでお風呂の温度を高めに設定するご家庭も多いと思いますが、熱いお湯に長時間浸かると、皮膚の保湿成分(セラミド)が流出します。大人の皮膚の表皮は0.02mmですが、子供はその半分以下の薄さです。そのため、大人と同じように入浴させると、乾燥肌が悪化する場合があります。お湯の温度設定は38度~40度のぬるめで、5~10分程度浸かるのを、目安にするのがいいでしょう。またスポンジやナイロンタオルでゴシゴシ洗うのは肌に負担をかけて、乾燥を招きます。石けんをたっぷりと泡立てて、素手で優しく洗ってあげましょう。
また、空気乾燥は乾燥肌を招く原因になるので、加湿器などで室内の湿度を適度に保つことにより、健やかな肌状態をキープできます。室内での快適な湿度は40~60%といわれていますが、50%を目安に湿度を調整するだけでも、肌の水分の蒸散が防げて、肌乾燥が和らぎます。加湿は、風邪や
インフルエンザ、新型コロナなど気道感染症にも有効です。
保湿は外側からのスキンケアだけでなく、こまめな水分補給で内側からケアすることも大切です。
冬場は、水分補給が少なくなりがちです。注意しましょう。
最後に、子供は痒みを我慢できずに掻いてしまうことがあるので、肌を掻いても傷がつかないように、日頃から爪を短く切っておくのも効果的な予防法です。
冬の乾燥から子供の肌を守るための基本は、「清潔を心がける」「乾燥を招く要因を減らす」「保湿
ケア」の3つです。
乾燥が気になる場合、保湿剤を塗る回数を増やしても大丈夫ですが、痒みや炎症が強くホームケアでは改善しづらい場合は、医療機関を受診しましょう。
こどものクリニック中山医院 院長
栄養士講座「炭水化物(糖質)は適量摂取が大事です」
日々秋めいて紅葉が待ち遠しい季節です。
さて、皆さんは炭水化物と糖質の違いを知っていますか。いわゆる糖質とは、消化・吸収にすぐれていて利用しやすいエネルギー源になるものです。食物繊維は、エネルギー源になりにくいですが、さまざまな生理機能があります。この糖質と食物繊維をあわせて、炭水化物と考えます。
最近では、糖質オフなど、炭水化物自体を減らすダイエット法などが注目されていますが、そもそもヒトが活動するエネルギー源として、炭水化物は欠かせません。
1日に摂取するエネルギー量のうち、50~65%エネルギー比が必要とされています。例えば、1日に2000Kcal摂取なら、そのうちの1000~1300Kcalは炭水化物から摂取することになります。
もちろん糖質を摂りすぎると、エネルギー過多や体内で脂肪に変わって蓄積されます。
減らし過ぎても、エネルギー不足、栄養素のバランスの崩れが起こりやすいなどがあげられます。
糖質は自分にあった適量を知って摂取することが大切といえます。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
栄養士講座「食物繊維をしっかり摂りましょう」
だんだん涼しくなってきて、食欲の秋到来ですね。
食べ物を食べると、栄養の大部分は小腸で吸収され、残りは大腸へ送られます。水分は腸内を移動している間にどんどん吸収され、便塊を形成し排便されます。便通を整えるには、食物繊維がとても大切です。食物繊維には、水に溶ける水溶性食物繊維と、溶けない不溶性食物繊維があります。水溶性食物繊維は、腸の中でゲル状になり、便の移動をスムーズにします。海藻類、こんにゃく、大麦、野菜などに多く含まれます。不溶性食物繊維は、胃や腸で水分を吸収して膨張し、便の量を増やします。穀類、野菜、きのこ類などに多く含まれます。どちらも摂取できると良いですね。
便秘の人は、規則正しい食習慣が出来ているか見直してみましょう。1日3食決まった時間に食事を食べること、主食・主菜・副菜をそろえて食べることを心がけます。そして、水分が少なくならない
ように1日に大人で1.2~1.5ℓ程度の水分摂取が必要です
栄養相談では、便秘や食物繊維の多いものなどのアドバイスをさせていただいていますので、
お声掛けくださいね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
院長講座「便秘症」
便秘症は、「よくある病気で、たいしたことではない」と 考えられがちですが、便秘症のお子さんは、便をするときに とても痛い思いをしたり、苦しんだりしてることが多く、 決してほっておいてよい病気ではありません。
また、便秘症は、放置しておくとだんだん悪くなることが多い病気です。その理由は、硬い便を出して肛門が切れ、痛い思いをすると、小さいお子さんは、排便の必要性を理解していないので、次の排便を我慢したり、肛門の筋肉を締めながら息むようになります。極端な例では、両足を閉じて便を我慢します。便はしばらく我慢していると、出たくなくなりますから、そのまま大腸に便が残ります。すると便はどんどん硬くなり、いよいよ出る時には非常な痛みをともなうことになり、お子さんは益々便を我慢するようになり、悪循環となります。そのようなことが続いていると、腸がだんだん鈍感になっていきます。すると便が長く腸にとどまって硬くなっていきます。このような2重の悪循環がおこるために、慢性の便秘症となってしまいます。そして、慢性の便秘症を放置すると、きちんと排便する機能が備わらず、大人になった後も便秘で悩むようになる場合があります。また正しい排便習慣を身につけないと、イライラや多動などその子の精神状態にも悪影響を及ぼす可能性があるとも言われています。
では、具体的にどのように対処すれば良いでしょうか。大きく食事などの生活から改善させていくものと薬剤などでサポートするものがあります。
食事は、食物繊維を多く含む、食材を使った料理がおすすめです。リンゴやバナナ、じゃがいも、さつまいも、納豆などの食材を毎日の食事に積極的に取り入れるほか、腸の動きを良くしたり、便を柔らかくしたりする効果が期待できるオイルの追加もおすすめです。スープや煮物などにオリーブオイルなどを入れてあげることで、排便状態を改善させられる場合があります。また、規則正しいトイレの時間を作ることも大事で、毎日決まった時間に排便をする習慣を、身につけさせてあげるようにしましょう。よく水分を増やすことが便秘を改善させると思われがちですが、水分量を増やしても便秘は改善されないことがわかっています。このようなご家庭でのケアを行っても、便秘症が改善できないような場合、すでに排便を我慢する傾向にある場合は、便を柔らかくするお薬や、便を出しやすくするお薬などを使った薬物療法を行います。
先に触れましたが、便秘症は早くからサポートすることが大切です。排便を嫌いになっている様子があれば、早期からお薬のサポートを行うことが重要です。
こどものクリニック中山医院 院長
栄養士講座「体内時計を正常に動かしましょう」
まだまだ暑い毎日です。夏休みも終わり、生活リズムの崩れがないか見直したい時期ですね。
皆さんは体内時計と生活の関わりについて知っていますか?
人間は、光も音も温度も分からない場所で生活すると25時間周期で寝起きをするといわれています。1日は24時間ですので、このズレを調整しているのが体内時計です。
体内時計を正常にはたらかせるには次の4つのことが大切です。
① 朝の決まった時間に太陽の光を浴びる
② 昼間はなるべく外に出る機会を増やす
③ 一般的な社会の生活リズムにあわせる(朝起きて活動をして、夜は睡眠をとる)
④ 1日3回の食事を規則正しくとること
また、朝食を食べることで体内時計のリセットが出来ると考えられています。朝食を欠食した場合では体内時計が後ろに引っ張られるため、代謝・吸収に影響が出るそうです。ですので、朝の光を浴びることと、朝食を食べて体にスイッチを入れること、まずはこれが出来ているのか見直してみてはいかがでしょうか。
メイプル管理栄養士 佐野 文美