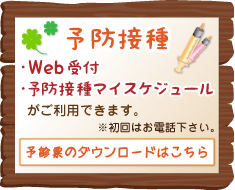今年のインフルエンザの流行は早いかもしれない
沖縄県でインフルエンザが流行しています。那覇市や浦添市では、定点あたりの患者報告数が10人を超え、注意報を発令しているようです。全国的には大きな流行にはまだ至っていませんが、今季は例年よりも流行時期が早く、学年・学級閉鎖も増えつつあります。
国立感染症研究所によると、第41週(10月10日~16日)の患者報告数は、全国で1,158人。定点あたりの患者報告数は0.24人。都道府県別では、沖縄県の7.03人が突出しています。定点あたりの患者報告数が1を越えると流行となります。首都圏でも学級閉鎖が9月からみられます。
ここからは私論ですが、例年RSウイルス感染の流行が終わるとインフルエンザの流行が始まる傾向にあります。今年は、夏の終わりの早い時期からRSウイルス感染の流行がありますので、RSウイルス感染の流行が例年より早く終わることを考えても、インフルエンザの流行が早くからくることも予想できます。
ワクチンを早めに打った方が良いかもしれません。
初冠雪
生後6ヶ月までのインフルエンザ予防には妊婦のワクチン接種が有効
妊娠中にインフルエンザの予防接種を受けた女性から生まれた乳児は非接種妊婦から出生の乳児に比べ、生後6カ月以内のインフルエンザ様症状発症のリスクが64%、インフルエンザの罹患リスクが70%、インフルエンザによる入院リスクが81%、有意に低下していたとの研究が報告されました。米国小児科学会の論文で紹介されています。
この論文では24万5386人の女性のインフルエンザワクチン接種状況、及びその乳児24万9387人のインフルエンザ様の症状の発症率などを比較しています。
また、インフルエンザと確定診断された乳児の97%は、母親が妊娠中にインフルエンザワクチンの接種を受けていませんでした。
研究グループは、今回の研究によりインフルエンザ接種推奨年齢に達しない生後6カ月未満の乳児をインフルエンザから守るため妊婦にワクチンを接種する公衆衛生面での意義を裏付けるエビデンスがさらに強化されたと話しています。
食物を床に落としたときの「5秒ルール」の真実
食物を床に落としても、すぐに拾えば大丈夫―そんな「5秒ルール」を使ったことのある人は多いだろう。しかし、その食物が本当に安全かといえばおそらくそうではなく、細菌汚染は1秒未満で発生しうるという調査結果が報告されました。
研究を実施した米ラトガーズ大学(ニュージャージー州)のDonald Schaffner氏らは、スイカ、パン、グミのキャンディなど、性質が異なるさまざまな食物を、セラミックタイル、ステンレススチール、木、絨毯などの面に落下させ、どのくらい菌がつくかを評価しました。それぞれの面はEnterobacter aerogenesというサルモネラ菌に似た細菌で汚染し、完全に乾燥させた後、食物を落として接触させました。
接触時間がそれぞれ1秒未満、5秒、30秒、300秒の場合にわけて、面から食物への細菌の移行率を評価した。128種類のシナリオを各20回、計2,560回の測定を行った結果、細菌の移行率は、細菌に汚染された面への曝露時間の長さと、食物の水分によって上昇していたようです。ただし、細菌汚染は1秒未満でも起きうることも判明しました。
Schaffner氏は、「細菌の移行リスクは食物の水分に最も影響されるようである。細菌は足があるわけではないので、水分を伝って移行するからだ。また、通常は、食品の接触時間が長いほど細菌汚染も多くなった」と話しています。実際に食物を落としたときの汚染リスクは、スイカで最大、グミのキャンディで最小であった。絨毯に落とした場合はタイルやステンレススチールよりも汚染が少なかった。木に落とした場合は汚染レベルにばらつきがあったという。
小児科医から育メンの勧め
米小児科学会が父親の育児における役割に関する報告書“Father’s Role in the Care and Development of Their Children”を発表しました。
この報告書では、「父親」ならではの関わりが、子供の健康に与える影響について3つ挙げています。
- ・父親による遊びはより興奮度が高く、活気にあふれている。父親とのいわゆる「はちゃめちゃ(rough and tumble)」な関わり合いで子供はリスクの範囲(safe risk)を知り、母親との大人しめの関わり合いで安心と均衡を得る
- ・父親は乳幼児に対し、言語発達を促しうる新しい言葉を話そうとする傾向が高い。子供が3歳時点の父子のコミュニケーションでその後の言語発達を予測することができる
- ・父親と十分な関わりがある思春期の小児は高リスク行動を起こしにくく、抑うつ症状にかかりにくい。幼少期から父親と十分な関わりがある女児は早発思春期のリスクが低下する他、早期の性活動や若年での妊娠が少ない
休みの日だけでなく、毎日の子供との関わりってとても大事なんです。