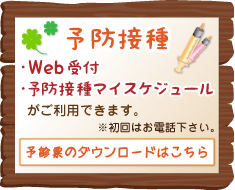~ 栄養士講座 ~ 「 睡眠時間の見直しをしましょう 」
入園、入学、進級などで生活リズムが変わりやすい時期です。こどもたちの睡眠時間について考えたことはありますか。
適切な睡眠は心身の休養と脳と身体を成長させる役割があります。睡眠時間が不足すると、
肥満のリスクが高くなる
抑うつ傾向が強くなる
生活の質(QOL)が低下する
ことが分かっています。生活習慣に関連する睡眠不足を防止する観点から、1~2歳児は11~14時間、3~5歳児は10~13時間、小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保することが推奨されています。成長期である高校生までは、成人よりも長い睡眠時間が必要ですが、一般に成長時期が進むにつれ、睡眠時間の確保が難しくなることもあります。もちろん個人差はありますが、十分な睡眠時間が確保できるように保護者が援助することが望ましいでしょう。思春期が始まる頃から、睡眠と覚醒のリズムが後退し、睡眠の導入に関わるホルモン(メラトニン)の分泌開始が遅れることで夜寝る時間が遅くなり、朝起きるのが難しくなる傾向がみられます。部活動や勉強、デジタル機器の使用などで睡眠不足になりやすくなります。朝は日光を十分に浴びて、朝食をしっかり食べること、座りっぱなしの時間を短くして運動をすること、デジタル機器は寝室に持ち込まないことなど、予防対策をして、夜更かし朝寝坊のような状態にならないように気をつけましょうね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野 文美
~ 中山通信 ~ 「麻疹(はしか)について」
- 麻疹(はしか)の国内発生が近年問題となり、先日も報道がありました。これは、コロナ禍の影響での、麻疹ワクチン(現在はMRワクチン)の接種率の低下により、社会の免疫の低下からきています。特に麻疹は感染力が強いので、地域での麻疹の発生を防ぐには、地域全体の予防接種率が95%を超えないと難しいと言われています。現在、日本でも、地域の接種率が95%以下の地域が多く、この状況が続く限り、また同様に、国内発生が起こると考えられます。このことは、世界も同様に起こっており、ロンドンや、ニューヨークでの麻疹の流行も見られています。
WHOは、新型コロナ感染症の影響や紛争の増加により、麻疹(はしか)の予防接種率が数年にわたり世界中で低下し続けた結果、2022年は、世界の麻疹の患者数の増加と、死亡者数が43%増加したことを報告しました。この報告書によると、2022年の麻疹患者数は900万人、死亡者数は13万6,000人とされ、そのほとんどは小児でした。報告書では、大規模または破壊的な麻疹のアウトブレイクが発生した国の数は、2022年には37カ国に増えたことも指摘されていて、国を地域ごとに見ると、最も多かったのは、アフリカで28カ国、次いで、東地中海地域6カ国、東南アジア2カ国、ヨーロッパ1カ国の順でした。
麻疹は予防接種を2回受けることで予防可能な疾患ですが、麻疹ワクチン未接種の小児の数は3300万人(初回接種を受けていない小児が約2200万人、2回目の接種を受けていない小児が約1100万人)に上ると推定されていて、2022年の世界全体でのワクチン接種率は、初回が83%、2回目が74%であり、集団免疫を獲得し、地域社会を麻疹のアウトブレイクから守るのに必要な2回目接種率(95%)を大きく下回っています。特に、低所得国では、麻疹ワクチンの初回接種率が、2019年から2021年の間に71%から67%へ低下し、2022年にはさらに低下して66%と、経時的に低下し続けています。
さらに、麻疹ワクチンの、初回接種を受けなかった2200万人の小児の半数以上が、わずか10カ国に住んでいることも示されました。それらの国は、ナイジェリア、コンゴ民主共和国、エチオピア、インド、パキスタン、アンゴラ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、マダガスカルでした。(W H O HealthDay News 2023年11月16日)
今回の麻疹の国内発生は、予想できたことで、起こるべきことで起きたとも言えます。麻疹の危険を地域から無くすには、このような危険性を国が皆さんにしっかりと啓蒙することが必要と私は思います。
中山医院 院長 中山豊明
~栄養士講座~ 「身体活動量を増やそう」
健康づくりには運動することが欠かせないことは知られていますが、日本におけるガイドラインが2023年に更新されました。健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023といいます。身体を動かす時間が少ないこどもには、何らかの身体活動を少しでも行うことが推奨されています。
身体活動は、体力(全身持久力や筋力)、心血管代謝機能、骨の健康、認知機能、メンタルヘルスを向上させることと共に肥満を改善する効果があります。
また、座りっぱなしの時間を短くすることが大事とされています。座りすぎは肥満の増加、体力の低下、社会的な行動への不適応、睡眠時間の減少と関係しています。 スクリーンタイム(ゲームやスマホへの使用、テレビなどスクリーンの前で過ごす時間)が長いほど、好ましくないメンタルヘルス、睡眠時間への悪影響を及ぼすことが分かっています。学習以外でスマホ・タブレットなどの画面を見る時間が1日2時間以上の者の割合は、令和4年の調査で小学5年の男子で62%、女子で54%、中学2年の男子で73%、女子で70%でした。余暇のスクリーンタイムが長くならないように、時間を決めて使用することが大切です。
外遊びの時間を作って運動の機械を増やすとよいですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「腸内環境を整えましょう」
ヒトの腸は、食べ物を消化し、栄養素の吸収を行っています。
他にも、水分を吸収して便を作り、体外に排出する役目があります。
また、腸には体内の半分以上の免疫細胞が集まっており、食べ物と一緒に運ばれてくる細菌やウイルスなどの異物や害を及ぼす外敵から体を守る役割もあります。
感染症予防対策や、自分が持っている免疫機能を最大限発揮するためには、バランスの良い食事を規則正しい食習慣でとることが最も重要です。
そしてバランスの良い食事をとりながら、心がけておきたいのが腸内環境を整えることです。
ヒトの腸管、主に大腸には約1000種類、100兆個の腸内細菌(腸内フローラとも呼ばれます)が生息していることが知られています。
体の健康を保つためには、腸内にビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌と呼ばれている菌が占める割合を増やすことが大切です。さらに、善玉菌を増やす水溶性食物繊維やオリゴ糖を十分に摂って、腸内細菌と健康を作ることも大切です。
最近では腸活という言葉もありますね。
善玉菌が多い食品は、ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、漬物などです。
とはいえ、これらの食品だけを摂ればいいのではなく、バランスの良い食事を摂ることを基本にし、食生活のプラス要素として考えると良いですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~院長講座~「熱性けいれんの対処法」
Q 熱性けいれんの対処法について教えてください
熱性けいれんは非常にポピュラーで、6ヶ月から6歳の13~30人に1人 の割合で見られます。
乳幼児の脳の細胞は未発達で、わずかな刺激で脳の細胞が過剰興奮して、それを抑制する働きも未発達なために起こると考えられています。
お子さんがけいれんした時は慌ててしまいますが、落ち着いてよく観察をします。
舌を噛むことを恐れて、無理に口を開け指を突っ込むことは、絶対にしてはいけません。これは舌を押し込んで気道を塞ぎ、窒息する恐れがあるためです。
● 衣服を緩めて平らなとこに寝かせ、吐いたものが詰まらない様に顔は横向きに
● 落ち着いてけいれんの時間を計りましょう
● 体の突っ張り方やふるえ方が左右対称かどうかをチェックしましょう
熱性けいれんであれば、何も特別なことをしたり薬を使ったりしなくても、数分以内に自然に止まります。 脳に障害をおこすこともありませんし、命に関わるようなことはありません。
● 10分以上けいれんが続く時
● 意識が戻らない時
→救急受診が必要です。
また、けいれんがおさまり、意識が戻っていても、熱を伴うけいれんは鑑別疾患に髄膜炎など緊急の病気も含まれるので、早めの受診をしてください。
中山医院 院長 中山豊明