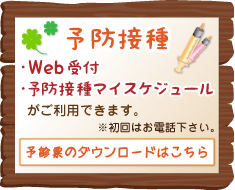~栄養士講座~ 「野菜を食べよう」
野菜にはそれぞれ様々な栄養素が含まれています。多種類の野菜の多様な成分が相互に作用しあって、体内で多くの大切な働きをしています。野菜の働きは
●食べすぎを防ぐ…満腹感を得られやすいです
●腸内環境改善…食物繊維が腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えたり便秘を防いだりします
●ストレスに対抗する…野菜のカロテン、ビタミンC、ビタミンEは抗酸化作用が強く、活性酸素を除去します
●血中脂質などの改善…水溶性食物繊維には血糖上昇抑制、コレステロール値や中性脂肪値を低下させる働きがあります
●血圧上昇抑制…野菜に豊富に含まれるカリウムは余分なナトリウムを体外に出して血圧上昇を抑制する効果があります
私たちの体調は、季節の変化に強く影響を受けており、冬には体が冷えて血液
循環が滞ったり、乾燥して空咳が出たり、皮膚がカサカサしたりします。
季節の野菜には、それらの症状を緩和する力を持つものが少なくありません。
冬の日本の旬の野菜は、白菜、かぶ、ほうれん草、ブロッコリー、長ネギなどがあります。毎日手軽に食べる習慣が出来ると良いですね。茹でたりスープに入れたりして、取り入れてみてください。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「味覚について」
毎日の食生活の中で、こどもに対して好き嫌いなく何でも食べてほしいと願うのはどの保護者も同じです。しかし、実際にはこどもの好き嫌い・偏食についての
悩みがあって、特に野菜嫌いの子が多いのはどうしてでしょうか。
ヒトの舌には味覚センサーの働きを持つ味蕾という細胞があります。この味蕾の数は、大人に比べて小さなこどもに多く、味に敏感であるといわれています。
私たちが感じる味覚には、味の基本五味というものがあります。
「甘味」「塩味」「旨味」「酸味」「苦味」の5つです。
このうち甘味、塩味、旨味は私たちが生きていくために必要な栄養素である糖質、ミネラル、たんぱく質(脂質の一部も旨味として感じます)を感じるシグナルで、本能的に必要なものとして好むと考えられます。
一方、酸味と苦味はどうかというと、酸味は腐敗した味、苦味は毒の味として認識し、口の中に入れてはいけない有害なもののシグナルとして受け取ります。
酸味や苦味の強い野菜は本能的に避けてしまうのです。
しかし、食経験を積むこと、例えば周りの大人がおいしいと食べている所を見ることや、頑張って食べることで褒められた経験で食行動に変化が出てきます。
食への興味を持ってもらうことも大切ですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~ 「体調の悪い時には消化の良い食事をしましょう」
発熱や、嘔吐・下痢などを伴う体調不良の時、食事はどうしたらいいのか悩んでしまうことはありませんか?
症状が強い時には無理せず、脱水症状を防ぐために水分補給をしっかりする
ことが大切です。冷たいものより常温のスポーツドリンクなどを少しずつ数回に分けて飲みます。
症状が落ち着いてきたら、体力の回復をはかるため、充分な栄養が必要です。この時には消化されやすいものを選んで食べるようにしましょう。
ゆっくりよく噛んで食べると、胃や腸に負担がかかりにくくなります。
消化されやすい食品は、おかゆ、パンがゆ、煮込みうどんなどがあります。
おかずを食べられそうであれば、鶏ささみ、豆腐、卵豆腐、半熟卵(生卵は消化が悪いです)、納豆、白身の魚、大根、かぶ、じゃが芋、かぼちゃ、にんじん、ほうれん草の葉先などを組み合わせると良いですね。おすすめの調理方法は、みじん切り、千切り、すりおろしです。皮や種は取り除いて、食材をやわらかくなるよう十分に加熱して食べてくださいね。
果物の中では、りんごとバナナは消化されやすく食べやすいです。
濃い味付けは避けて、症状をみながら、1週間くらいかけて普段の食事に近づけていきましょう。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~栄養士講座~「食育の意識を知ろう」
「食育」が大切といいますが、実際にどのようなことを指すのか知っていますか。食育は生きる上での基本であり、知育・徳育・体育の基礎として位置づけられるとともに様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てるものといわれています。
食育が重要とされる背景には、
●栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満やそれらが原因と考えられる生活習慣病の増加がみられること
●若い女性を中心にみられる過度なダイエット志向や、高齢者の低栄養などの健康問題も
指摘されています。
こうした中で、食に関する知識を身につけて健康的な食生活を実践することで心と体の健康を維持し、生き生きと暮らすために、食育を通じて生涯に渡って食べる力と生きる力を育むことが重要とされています。
食育によって身に付けたい食べる力は、
●食事を通じて心と体の健康を維持できる
●食事の重要性や楽しさを理解する
●食べ物を自分で選択し、食事づくりができる
●家族や仲間と一緒に食べる楽しみを味わう
●食べ物の生産過程を知り、感謝する気持ちを持つこと
などです。
子どもの頃から、家庭や学校、地域など様々な場で学び、身に付けていくことが大切で、さらに大人になってからも生涯に渡って実践出来るようにしたいですね。
メイプル薬局管理栄養士 佐野文美
~院長講座~「インフルエンザ罹患後の接種」
Q 先日インフルエンザにかかってしまいましたが、
この冬のインフルエンザワクチンは受けた方が良いでしょうか
インフルエンザは、「1シーズンに1度感染すれば、そのシーズンはもう感染しない」というものではありません。今年は、冬にA型インフルエンザにかかった人で、最近、A型のインフルエンザに罹患した人も数人いらっしゃいました。
ヒトが感染するインフルエンザウィルスには大きく分け4種類あり、
さらにA型ウィルスは構造によってさらに多くの種類があります。それらのウィルスはさらに小さな変異を繰り返すので、まったく同じウィルスにしかかからない保証はありません。
同じインフルエンザでも、種類が違えば別のウィルスなので、免疫ができていても感染してしまうのです。
このことから、同じウイルスでも小さな変異を起こせば、この冬に感染する可能性があること、インフルエンザウイルスには4種類の流行型があり1度かかっても他の3つにかかる可能性があることが考えられますので、
「今年インフルエンザにかかってもワクチンを打つ意味がある」ということになります。
インフルエンザは一度かかると高熱や咳・鼻水・全身のだるさ・筋肉痛といった症状が5日から7日程度続く、たいへんしんどい病気です。
ワクチンで予防、軽症化させることをお勧めします。
中山医院 院長 中山豊明